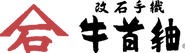牛首紬について
メニュー
「最初に入った糸挽の部屋には、ノベ釜といわれる鉄釜にあふれるほどの繭を煮立てていた。掻きまぜて、ほぐれた糸の緒は数条あわせて後の枠に捲きとられる。室内にはもうもうと立ち籠めた湯気で、一種独特の繭を煮る匂いがする。そこに座ってつむぐ女たちの顔も服も一様に、乳白色の湯気にすっぽりと包まれ、時折窯を火からおろすたびに見える火色が美しい。ぐらぐらと煮え立つ大釜に百を超すと思う繭玉が、浮き沈み、やわらぎながら女たちの澱みなく動く手に従っている。繭糸はしだいにほぐれ、やがて夥しい褐色の蛹が現れる。それはまるで蚕が糸をはき出すように、音もなく縷々と立ち昇り、光を出すのだ。」
「この日たった一人の織女が、黙々と白生地を織っていたのだが、生地は雪のように白く、いかにも侘びしい白山山麓のたたずまい表徴するかの如くであった。まもなく冬が来て、当然のように厚い雪の層にすっぽりとつつまれるこの薄暗い家の中で初めて外界に触れて生まれる白生地は、さぞ初々しく魂にしずもりを与えてくれることであろう。それはあでやかではないが、山家に育つ女の持つ素朴な艶がにじんでいるようでもある。そのさわやかな気品はそれを作った女たちの生きる身構えの精魂がにじんでいるからに相違いない。」
井上雪 著「聞きがき抄 北陸に生きる女」より抜粋
「この日たった一人の織女が、黙々と白生地を織っていたのだが、生地は雪のように白く、いかにも侘びしい白山山麓のたたずまい表徴するかの如くであった。まもなく冬が来て、当然のように厚い雪の層にすっぽりとつつまれるこの薄暗い家の中で初めて外界に触れて生まれる白生地は、さぞ初々しく魂にしずもりを与えてくれることであろう。それはあでやかではないが、山家に育つ女の持つ素朴な艶がにじんでいるようでもある。そのさわやかな気品はそれを作った女たちの生きる身構えの精魂がにじんでいるからに相違いない。」
井上雪 著「聞きがき抄 北陸に生きる女」より抜粋
これは、昭和49年に随筆家の井上雪氏により書かれた加藤手織牛首つむぎの作業場の風景である。それから40年余りが経った今も、ほとんど変わらない方法で仕事が続けられている。先祖が繋ぎ続けてきた白山市桑島に伝わる文化と伝統を後世に伝えていかなければならない。